1)炬火
後には、2尺も3尺もある長い松明ができたが、裸ろうそくやマッチの軸木なども、皆一つの手火である。
夜分に2里も3里も歩かなければならない時には、必ず松明をともして出かけた。それが、提灯の普及するまでの、屋外のあかりのたったひとつの方法であった。
夜通し道を歩く者、夜の山で狩りをするような人達は、背中に大きなかごを背負って、沢山の松明をその中に入れて出かけた。
それが提灯の発明により、僅かなろうそくと一つの提灯で、用が足りるようになったのだから、誰もが利用するようになった。
松明は、松以外の材料を使ったものも多い。
麦わらタイマツ。竹のタイマツ。などなど。
また、檜の薄い削りくずを集めて作ったもの、などもあった。これは商品にもなり、大きな交通路の道端では、これを並べて旅人に売っていたようだ。
檜のくずは、曲げ物細工をするときなどに出るもので、これを大事に取っておいて、御嫁入りとか晴れの旅立ちとかの、人に見られるような日の、松明に使おうとした。
紙の商売もなく、ろうそくを長く持たせる改良も無く、提灯の真ん中を丸くして火から遠ざける発明も無かった頃には、闇夜は松明よりほかに、道を明るくする方法がなかった。
2)灯籠
高いさおの先に火をあげて、空を来る神霊を案内する必要は、まだろうそくがなく、灯籠ができない以前からあった。(盆の火=迎え火、送り火)
柱松、といって、非常に長い柱のような松明を作って、その中にいくつものなわをつけておき、松明に火をつけてから引き起こす事にしていた。
しかし柱松明は、どんなに長くとも、燃えてつきてしまうので夜通しはともせない。だから材料の豊かな家では、何本もこれを作っておいて、順々に次の松明を建てていたかもしれないが、それではあまりに手数がかかるので、後にまた一つのおもしろい方法ができた。
それは、柱の先に籠を取り付けて、燃やす材料を置き、立てかけてから、下から松明に火をつけたのを投げ入れる、と言う方法である。これを投げ松明といっていた。
《これは、一種の競技となって、今日でも引き継がれている。いわるゆ「玉入れ」競技は、これの名残ではないか。=投稿者》)
(そうこうする中で)灯籠が入って来た。
高灯籠の普通のあげ方は、船の帆を引き上げるあのセビというものを用い、これに日本のつなをつけて、上げ下げのできるようになっていた。(燈籠木)
しかし、長い間、ろうそくをその燈籠につけておくことは、手数より費用がたいへんでよほどお金のある家でないとできない。
そこで、様々な工夫がなされた。(二通りの方法があった)
一つは、ろうそくの代わりに油をともす、一種の道具を用いた。それを燈蓋(とうがい)という。
燈蓋は口が浅いと油がこぼれるので、深い口のつぼんだ形にして、まん中に燈心をさす細い筒をたて、台を取り付けた。これを東北地方ではタンコロ、とか、タンコロリン、といっている。
もう一つは、ヒョウソクといった。
*丸提灯
提灯は、まず竹を細かく割って削る。それを輪にしたものをいくつも重ね並べる。そして、そのうえに紙をはる。
竹の棒(ヒゴ)の長さを違えることで、輪の大きさをかえて、丸みをだす。
という手順で作られた。
という手順で作られた。
―丸提灯―
*弓張り提灯
火をともした提灯をそのままにして、両手で仕事をしようとする場合に都合がいいようにするには、つっかい棒がないと、地面に置けない。
それで、様々な工夫がなされた。
最初はただ、木の枝か何かぶら下げておくなどして、下に置くことまでは考えなかった。やがて、棒をたてに通して支柱にすることを考案した。
さらに、クジラのひげを利用して、弓張りというものが発明された。
*箱提灯
提灯の口があまり小さいと空気の流れが悪く、口を大きく開ければ、よく燃えるかわりに、雨風を防ぐには都合が悪い。それで、上の方にフタをつけて、遠道をするときに使った。
この提灯には、紙には油がぬってあり、口にはフタがあって、松明とは違い、雨風の心配をしなくてもよくなった。
当然のことながら、これは紙の流通が一般化していて、紙が安い値段で手に入る事が前提である、と思われる。
当然のことながら、これは紙の流通が一般化していて、紙が安い値段で手に入る事が前提である、と思われる。
―箱提灯―
4)蝋燭(歴史、材料、灯心の工夫)
*歴史
奈良朝(奈良時代)の頃からすでにあったが、その用途は限られていた。また、高価で、分量も少なく、上流階級の人々でなければ使うことが出来なかった。(仏教の伝来との関係か?)
シナ(中国)から入って来た(戦国時代のころ?)ロウは、ミツバチの巣から取った蜜蝋であったらしい。それを裸のまま持つか、木の枝に刺すかしていた。
が、日本では日暮れや夜中に風のよく吹く国であるから、裸のままのろうそくは、ロウがかたよって溶けて無駄になりやすい。それを防ぐには、風よけの囲いが必要になる。
しかし、紙は高価なものであったので、誰にでも紙がたやすく手に入って、家に紙の窓が出来て部屋部屋が明るくなるのと同じころから、急にろうそくは国民の間で使われる様になって来た。(江戸期以後?)
そして、このころから、「ラッソク」といわずに、ろうそくと言う人が多くなってきたらしい。
*材料
日本では、はぜうるし(漆)の実から取っていた。(=和ろうそく)
一方、松脂(まつやに)ろうそくというものがあって、農家ではこれで間に合わせていた。
やがて、アブラナの普及するにつれて、菜種の油を使うようになった。ろうそくが一般に普及しだすのは、アブラナの普及から後のことであると思われる。(江戸時代以降)
*灯芯の工夫
ろうそくは、明治期になって急速に改良が進んだ。それは、芯の変化による。油を芯に染みこませて、火が長く燃えているようにするには、紙をまいて捻った紙芯を使った。(西洋ろうそくの輸入による)
それ以前には、とうきびなどの髄を使ったものもある。
紙は燃えれば灰になるからそのままにしてもよいが、とうきびの芯は何時までも太く残っていて、大きく火が燃え、ろうが早くとけるので、度々その芯を叩いて小さくする必要があった。
それで、この蝋燭を折檻ろうそくと呼んだ。こういう話もある。
しかし、どちらにせよ、火力が強くてロウが早く流れるので、細いろうそくを作る事が難しかった。
この芯を細くすることがひとつの発明で、小ろうそくが出来上がった。
★
★
元来、ろうそくは、芯切りの仕事が非常に面倒で、燭台の横の鉤には、必ず芯切りと言う金物のハサミが掛かっていた。そして、1人がつききりのようにして、その芯をハサミで切り取っていた。
浄瑠璃や芝居の舞台でこのようなろうそくを立てたところには、一人の芯切りの男がいて、あちらこちらと走り回って芯を切った。
燭台の下にはまた、切った芯を入れるための、ふたのある消壺のようなものがおかれていて、これを「ほくそほとぎ」といった。
ほとぎ、は、つぼのことで、たいていは土焼の器、後には真鍮などのものが出来た。
燭台と芯きりとつぼとは、三点セットであって、普通の家庭では欠くべからざる道具であった。
そうこうするうちに、西洋から、木綿をより合わせて芯にした糸芯が入って来た。それで、芯きりとつぼは不用品になった。
この芯を使ったろうそくはロウが少ししかとけないので、燈火が長く持つようになった。
―燭台の図―
参考文献
1)『柳田國男 全集 14』 筑摩書房
2)日本民俗建築学会編 「(図説)民俗建築大辞典 』 柏書房
3)日本民俗建築学会編 『日本の生活環境文化大辞典』 柏書房
4)宮崎玲子著 『オールカラー 世界台所博物館』 柏書房
5)大館勝治・宮本八恵子著『「今に伝える」農家のモノ・人の生活館』柏書房
6)柏木博・小林忠雄・鈴木一義編『日本人の暮らし 20世紀生活博物館』講談社柳田
2)日本民俗建築学会編 「(図説)民俗建築大辞典 』 柏書房
3)日本民俗建築学会編 『日本の生活環境文化大辞典』 柏書房
4)宮崎玲子著 『オールカラー 世界台所博物館』 柏書房
5)大館勝治・宮本八恵子著『「今に伝える」農家のモノ・人の生活館』柏書房
6)柏木博・小林忠雄・鈴木一義編『日本人の暮らし 20世紀生活博物館』講談社柳田
(2018年8月23日。最終投稿日2018年8月28日)
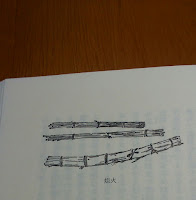



1 件のコメント:
補足:木綿が本格的に栽培され出したのは、16世紀以降とされる。戦国時代後期からは全国的に綿布の使用が普及し、三河などで綿花の栽培も始まり、江戸時代に入ると急速に栽培が拡大。各地に綿花の大生産地帯が形成され、特に畿内の大阪近郊などにおいて生産が盛んになった。
コメントを投稿